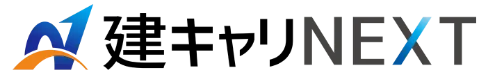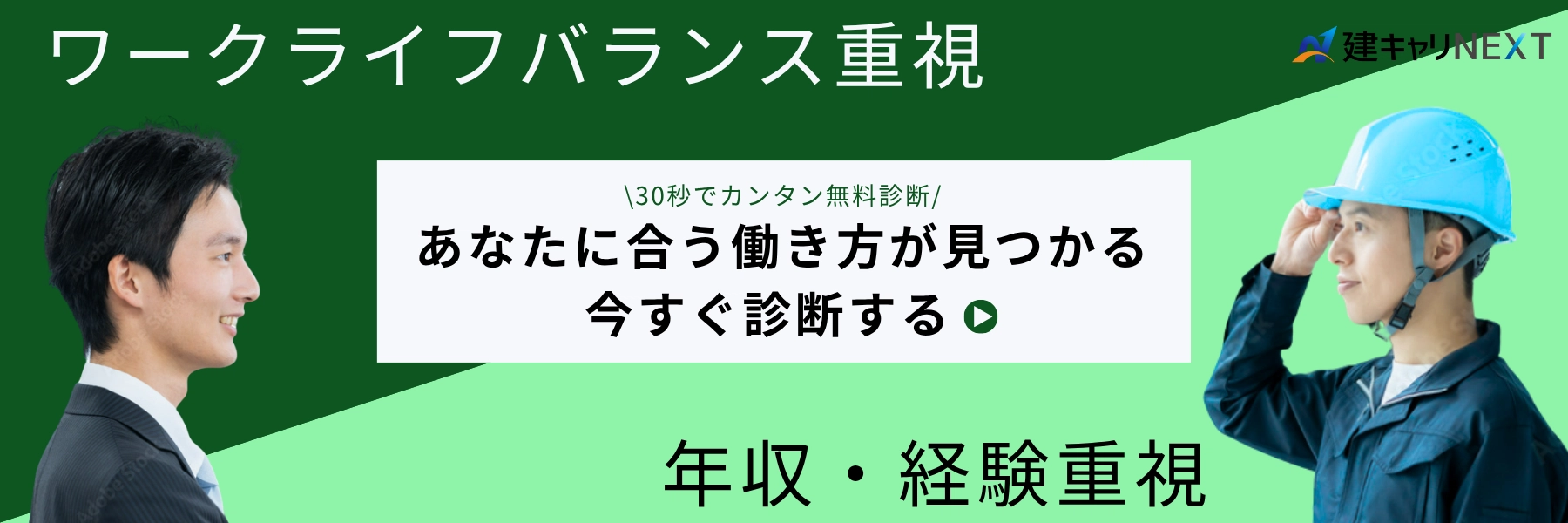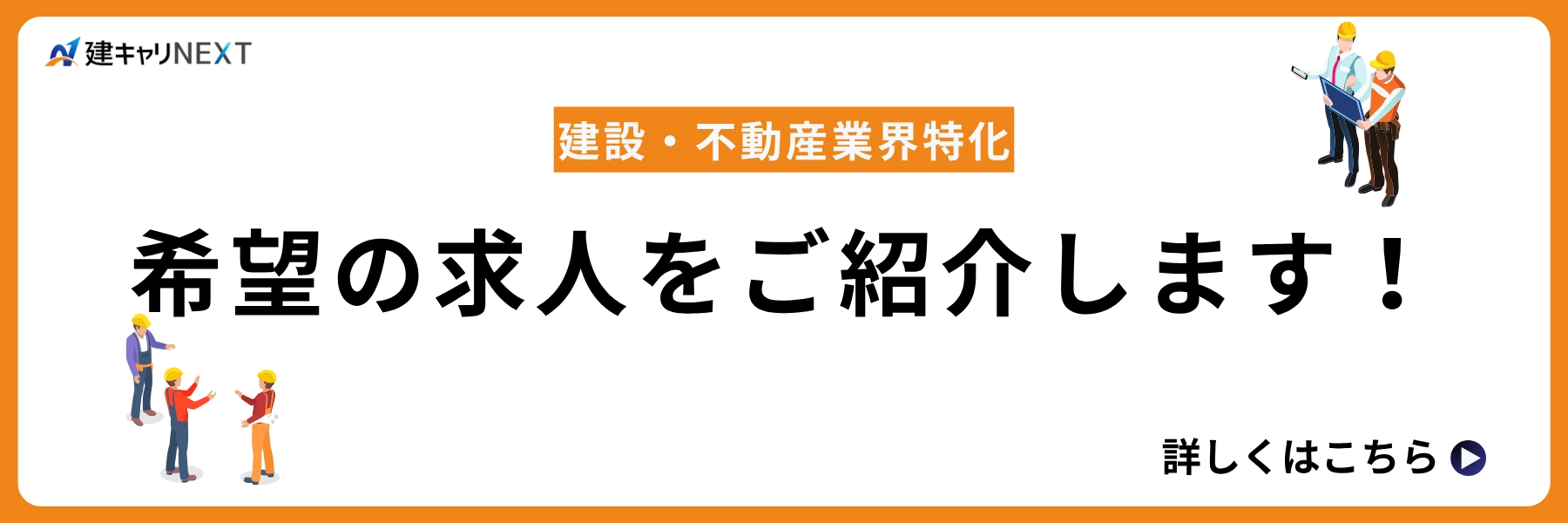建築士・設計士が知っておきたい確認審査機構と住宅性能評価の仕事は? 現役エージェントが徹底解説
更新日:2026年02月04日

記事まとめ(要約)
- 確認審査機構は、建築基準法に基づき建築物の適法性・安全性を審査する機関。デスクワーク中心で夜勤もなく安定した働き方が可能。
- 住宅性能評価は、品確法に基づき住宅の耐震性・省エネ性・耐久性などを等級化する制度。現場確認もあり、住宅性能の専門家としてキャリアを築ける。
- 年収は確認審査機構が400〜700万円、住宅性能評価が350〜650万円程度が目安。管理職では800万円クラスも目指せる。
- 転職活動では、一級建築士、省エネ適合判定員、構造・設備に関する実務経験などが強みとして高く評価される。
「確認審査機構ってどんな仕事?」「住宅性能評価との違いは?」──建築士や設計士の方でも、具体的な業務内容やキャリアの広がりについては意外と知られていないかもしれません。
しかし今、建築業界では確認審査機構と住宅性能評価の人材ニーズが急拡大しています。
建築基準法改正や省エネ基準の強化、脱炭素社会の実現に向けた動きにより、両分野の役割はこれまで以上に重要になっています。
本記事では、現役の転職エージェントが仕事内容・年収・働き方・必要資格まで徹底解説。転職を検討する建築士・設計士の方に向けて、キャリア選択のヒントをお届けします。

建キャリNEXT シニアコンサルタント
梶井 龍一郎
大学を卒業後、企画営業に従事
転職し20年以上人材業界に携わる。
現在は技術者をメインとしたキャリアサポートと人材教育を10年以上行っており、
累計6,000人以上の転職支援をサポートしている。
東京都出身、二児の父。
なぜ今、確認審査機構や住宅性能評価が注目されるのか
近年の建築基準法改正、省エネ基準の強化、そして災害リスクへの意識の高まりにより、確認審査機構や住宅性能評価の役割は急速に重要性を増しています。従来は行政が中心に担っていた業務を、指定確認検査機関(代表的な企業:日本ERI)などの民間企業も担うようになり、建築士や設計士にとって新しいキャリアの選択肢となっています。
建築士・設計士が注目する理由
施工管理や設計事務所の勤務は「長時間労働・夜勤・突発対応」といった負担が大きい一方で、確認審査機構や住宅性能評価はデスクワーク中心・夜勤なし・法令知識を活かせるという特徴があります。ワークライフバランスを重視しつつ建築士資格・設計経験を活かしたい人にとって注目の転職先となっているのです。
確認審査機構での仕事内容や年収と働き方について
仕事内容の詳細
確認審査機構で働く建築士や設計士の中心的な役割は、建築物が法令に適合しているかを判断する建築確認審査です。提出された設計図書をもとに、建築基準法・消防法・都市計画法などに照らして詳細にチェックを行います。主な審査項目には、容積率・建ぺい率の適合、避難経路の確保、防火区画の設置、耐火性能の有無などがあり、いずれも建物の安全性や住環境に直結する非常に重要なものです。
また、審査の過程で不備が見つかった場合は、設計事務所や施工会社と調整を行い、修正を依頼します。単に図面を確認するだけでなく、設計者と対話しながら法令適合を導くコンサルタント的な役割も担っているのが特徴です。場合によっては行政や他の専門機関ともやり取りを行うため、法令知識に加えてコミュニケーション能力が求められる仕事と言えるでしょう。
平均年収と待遇
確認審査機構に勤務する建築士の平均年収は400〜700万円が一般的な相場です。若手の二級建築士は400〜500万円程度からのスタートとなるケースが多く、一級建築士資格を有する人材や、構造計算・設備設計に精通した人材は、入社時から600万円以上を提示されることもあります。さらにマネージャーや部長など管理職に昇進すると、800〜900万円クラスまで年収が上がる可能性があります。
また、年収以外の待遇面として、住宅手当や資格手当が支給される企業も多く、専門性を高めれば高めるほど処遇に反映されやすい傾向にあります。特に指定確認検査機関の中でも大手の日本ERIなどは給与水準も安定しており、長期的に安心して働ける点が魅力です。
働き方の特徴
確認審査機構での働き方は、ゼネコンや設計事務所と比較すると残業が少なく夜勤もないという点で大きな違いがあります。業務は基本的にオフィスワーク中心で、審査対象の建築計画や住宅性能評価書類をもとに進めるため、現場対応で突発的に拘束されることが少ないのです。そのためワークライフバランスを重視したい建築士から高い人気を得ています。
ただし、繁忙期には審査件数が集中し、一定の残業が発生する場合もあります。しかし施工管理のように夜間工事や休日対応が頻発するわけではなく、働き方としては比較的安定しています。育児や家庭との両立を考える建築士にとっては、キャリアを継続しながら生活の質も守れる数少ない職場環境と言えるでしょう。
代表的な求人企業
- ・日本ERI株式会社(指定確認検査機関の最大手。全国展開し案件数・安定性が高い)
- ・株式会社住宅性能評価センター(確認審査と評価業務を兼ねる大手機関)
- ・株式会社東京建築検査機構(TBC)(首都圏中心。集合住宅・大型案件に強み)
- ・株式会社近畿建築検査センター(関西エリア中心。地域密着で安定した需要)
- ・一般財団法人日本建築センター(BCJ)(長い歴史を持つ公益的な検査・認証機関)
住宅性能評価での仕事内容や年収と働き方について
住宅性能評価の仕事内容
住宅性能評価は、住宅の性能を客観的に数値化・等級化する重要な業務です。対象となるのは、耐震性・耐久性・省エネルギー性能・劣化対策・維持管理の容易性など多岐にわたります。建築士は、設計図書や仕様書を精査し、必要に応じて現場確認を行いながら、耐震等級や断熱等級を付与します。これにより住宅購入者や入居者が安心して住まいを選べる環境が整えられます。
特に近年は、ZEH(ゼロエネルギーハウス)や長期優良住宅の普及、さらには脱炭素社会の推進により、省エネ性能や環境性能の評価需要が急拡大しています。単なる法令チェックにとどまらず、建築の品質向上や市場価値の向上に直結する業務であるため、住宅性能評価の専門性を高めることがキャリアの武器になります。
年収水準
住宅性能評価に携わる人材の平均年収は350〜650万円程度が一般的です。経験の浅い二級建築士や若手の場合は350〜450万円前後からスタートするケースが多いですが、省エネ適合判定員や構造計算の知識を活かせる建築士は高く評価され、500〜600万円以上の待遇を得やすくなります。さらにチームリーダーやマネージャーなど管理職に昇進すると、700〜800万円クラスに到達することも十分可能です。
また、一部の大手指定確認検査機関では、資格手当・研修制度・住宅関連補助など福利厚生も充実しており、専門性を高めた人材ほど年収と処遇が安定する傾向があります。
働き方の特徴
住宅性能評価業務の働き方は、基本的にはデスクワーク中心でありながら、必要に応じて現場調査を行う点が特徴です。図面審査に加え、施工現場で断熱材や構造部材の施工状況を確認することもあり、オフィスワークとフィールドワークの両面を経験できます。
繁忙期には申請件数が集中するため一定の残業が発生する場合もありますが、施工管理やゼネコン勤務のような夜勤や突発的な休日対応は少なく、ワークライフバランスを確保しやすい働き方といえます。特に「現場第一線から離れたいが、建築士資格を活かし続けたい」と考える方にとって、住宅性能評価は魅力的なキャリアの選択肢となっています。
代表的な求人企業
- ・株式会社住宅性能評価センター(住宅性能表示制度に特化。全国規模で展開)
- ・日本ERI株式会社(確認審査と併せて住宅性能評価業務も強み)
- ・ハウスプラス住宅保証株式会社(性能評価と瑕疵担保責任保険をセットで提供)
- ・株式会社ハウスジーメン(住宅性能評価や長期優良住宅認定支援に強み)
- ・株式会社日本住宅保証検査機構(JIO)(性能評価に加え、住宅保証事業を展開)
確認審査機構と住宅性能評価の比較
建築士や設計士がキャリアを検討する際に、確認審査機構と住宅性能評価は混同されやすい分野です。どちらも建築物の品質や安全性を保証する重要な役割を担っていますが、その目的・根拠法・評価内容・働き方には明確な違いがあります。ここでは両者を比較し、それぞれの特徴やキャリア選択におけるポイントを整理します。
確認審査機構と住宅性能評価の比較
| 確認審査機構 | 住宅性能評価 |
|---|---|
| 目的 | |
|
建築物の適法性・安全性を確認 建築基準法や消防法などへの適合性を審査し、社会的に安全な建物の実現を担う。 |
住宅の品質を客観的に評価 耐震性・省エネ性・耐久性などを数値化し、購入者や入居者に安心を提供する。 |
| 根拠法 | |
|
建築基準法 建築確認申請・検査の根拠となる法律。 |
住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法) 住宅性能表示制度を規定する法律。 |
| 評価内容 | |
|
建築基準法への適合性 容積率・建ぺい率、防火区画、避難経路、耐火性能などのチェック。 |
住宅性能10分野 構造の安定、省エネルギー性、劣化対策、維持管理対策などを評価。 |
| 発行書類 | |
|
確認済証・検査済証 建築計画が法令に適合していることを証明。 |
住宅性能評価書(設計・建設) 性能を等級で示した書類を発行し、取引時の信頼性を高める。 |
| 働き方 | |
|
デスクワーク中心で夜勤なし 図面審査が中心で、繁忙期以外は残業も少なく安定した勤務が可能。 |
デスクワーク+現場確認あり 書類審査と現場調査を組み合わせた働き方。安定感がありつつ動きもある。 |
| 給与・待遇 | |
|
平均年収400〜700万円 一級建築士や管理職で800〜900万円も可能。大手機関は給与水準が安定。 |
平均年収350〜650万円 省エネ判定員や構造に強い人材は高待遇。管理職は700〜800万円クラス。 |
| キャリアの将来性 | |
|
法令適合の専門家 行政・コンサルへの転職やマネジメント職に進む道もあり、安定感がある。 |
住宅性能の専門家 省エネ・耐震・長期優良住宅など需要拡大分野でキャリアを築ける。 |
転職する際に強みになる経験と資格
確認審査機構や住宅性能評価の業務へ転職を目指す際には、これまでの経験や保有資格をいかに整理して伝えるかが重要です。特に職務経歴書では、設計・施工管理などの実務経験や、建築士資格、省エネ関連資格などを具体的に記載することで、採用担当者に即戦力としての強みをアピールできます。ここでは、転職活動で評価されやすい経験や資格をまとめましたので、ぜひ自己PRや職務経歴書作成の参考にしてください。
共通して評価される経験・スキル
- ・設計業務の実務経験(意匠・構造・設備いずれも歓迎)
- ・施工管理経験(法規や施工品質への理解が評価に直結)
- ・法令知識(建築基準法、都市計画法、防耐火・避難規定など)
- ・行政・審査機関とのやり取り経験(確認申請・性能評価の実務に近い)
- ・コミュニケーション力(設計者や施工会社と調整する力)
確認審査機構で強みとなる資格・経験
- ・一級建築士(必須・推奨。法令審査や責任ある立場に直結)
- ・二級建築士(木造や小規模案件の審査で活躍可能)
- ・構造設計一級建築士(大規模建築・構造審査に強み)
- ・設備設計一級建築士(防災設備・省エネ設備分野で有効)
- ・一級建築基準適合判定資格者(確認検査員として、検査を行うことができる)
- ・二級建築基準適合判定資格者(確認検査員として、検査を行うことができる)
- ・確認申請業務の実務経験(設計事務所やゼネコンでの申請対応)
住宅性能評価で強みとなる資格・経験
- ・一級建築士(評価員として幅広い案件を担当可能)
- ・省エネ適合判定員(ZEH・長期優良住宅など省エネ分野で必須に近い)
- ・構造計算に関する実務経験(耐震等級の評価に直結)
- ・BELS評価員・CASBEE評価員(周辺制度の知識がプラス評価)
- ・現場監理経験(図面だけでなく現場での施工状況を評価する力)
まとめ|確認審査機構と住宅性能評価と転職について
確認審査機構と住宅性能評価は、いずれも建築士や設計士の資格を活かせる安定したキャリアです。
年収レンジは大きく変わりませんが、確認審査機構は管理職で高収入を狙いやすい一方、住宅性能評価は専門性を武器に需要拡大分野で活躍しやすい傾向があります。いずれの道を選んでも、職務経歴書に過去の設計・施工管理経験や関連資格を明確に書くことで、転職活動を有利に進められるでしょう。
転職を考える中で「自分にはどちらが合っているのか」「キャリアの先にどんな選択肢があるのか」と悩む方も少なくありません。
そんな時は、ぜひ一度私たちにご相談ください。
ご経験や保有資格、ライフスタイルに合わせて、最適なキャリアプランや非公開求人のご提案をいたします。
あなたの強みを最大限に活かし、納得できる転職を実現するために全力でサポートいたします。