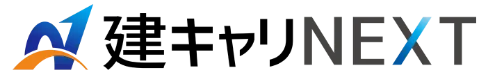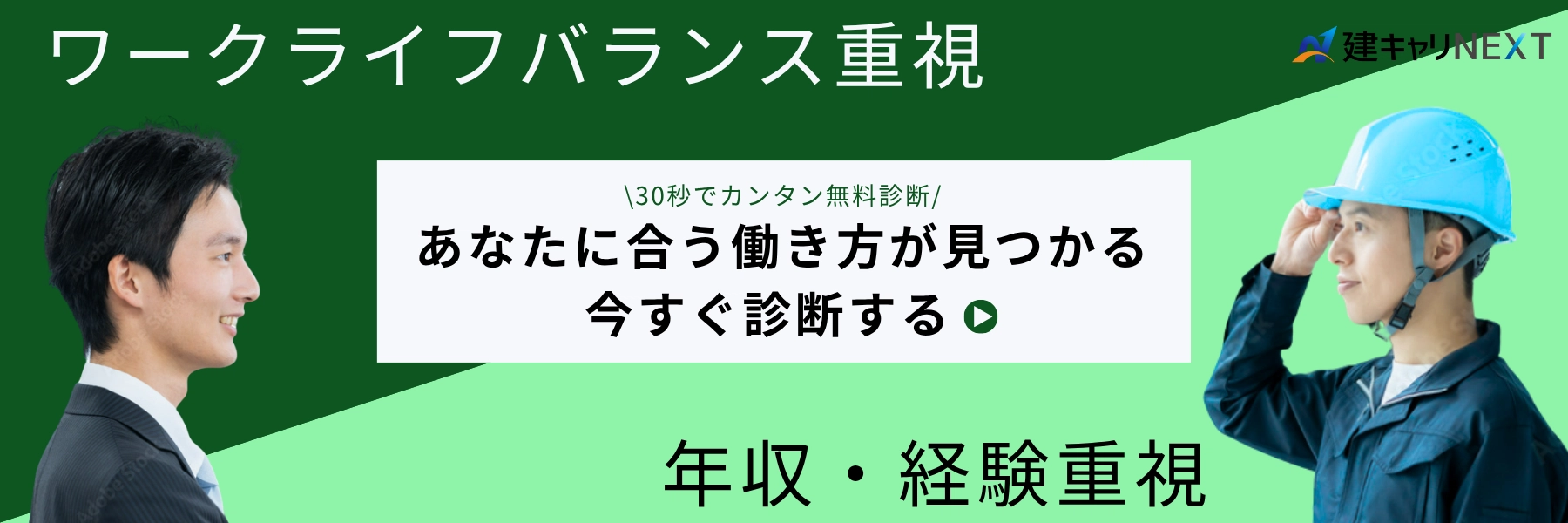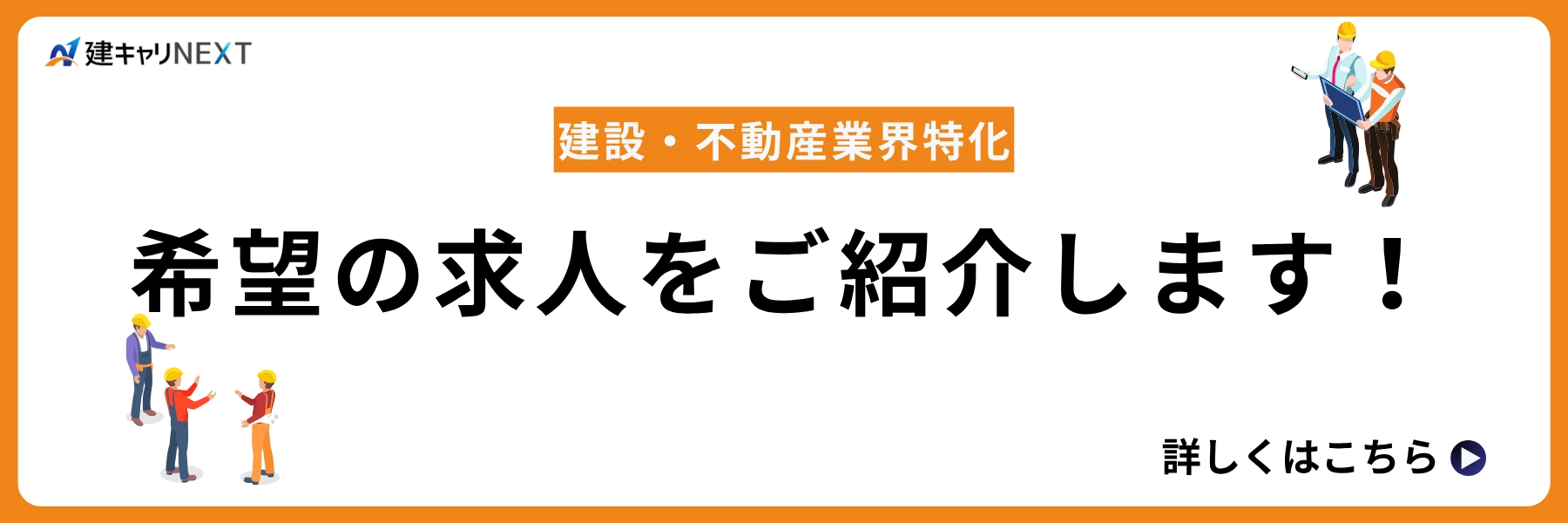一級建築士は本当に稼げる?取得するメリットと年収を徹底解説!
更新日:2025年06月17日

記事まとめ(要約)
- 一級建築士は扱える建物の構造や規模に制限がない
- 一級建築士試験の合格率8.8%(令和6年試験結果)
- 一級建築士の平均年収は、約700万円
- 一級建築士が活躍する企業三選は、【大手ゼネコン】・【ハウスメーカー】・【設計事務所】
建築業界でキャリアアップを目指す上で、多くの人が目指す「一級建築士」。国家資格の中でも難易度が高く、取得には相応の努力と経験が求められますが、その分“稼げる資格”としても知られています。とはいえ、実際にどのくらいの年収が見込めるのか、資格を取ることでどんなメリットがあるのか、気になる方も多いのではないでしょうか。
この記事では、一級建築士の平均年収データや、資格取得によって広がるキャリアの可能性、転職・独立時の価値などを徹底的に解説していきます。「一級建築士を取るべきか迷っている」「資格を活かして年収を上げたい」そんな方は、ぜひ参考にしてください。

建キャリNEXT シニアコンサルタント
梶井 龍一郎
大学を卒業後、企画営業に従事
転職し20年以上人材業界に携わる。
現在は技術者をメインとしたキャリアサポートと人材教育を10年以上行っており、
累計6,000人以上の転職支援をサポートしている。
東京都出身、二児の父。
一級建築士とは?資格と取得まとめについて
一級建築士は、扱える建物の規模や用途に制限がなく、都市開発や大規模建築など様々なプロジェクトに携われる点が大きな魅力です。
一級建築士は国土交通大臣が免許を交付する国家資格であり、建築業界における最高峰のプロフェッショナルとして認められています。建築設計や工事監理を幅広く手がけることができるため、公共施設や商業施設など大規模案件でリーダーシップを発揮するケースが増えています。特に都市部における超高層ビルなどを担当する機会も多く、モチベーション次第で活躍の場が大きく広がります。
この資格を持つことで業務範囲の制限が実質的に撤廃されるため、新築だけでなくリノベーションや耐震改修など多様なプロジェクトでスキルを発揮できるようになります。民間はもちろん、官公庁や教育機関などからの依頼も多く、唯一無二の専門家として安定した需要がある点もまとめの一つです。
さらに、一級建築士の肩書きはキャリア形成にも大きく役立ちます。設計事務所だけでなく、総合建設会社やディベロッパー、公共機関など幅広い組織から高い評価を受けやすく、責任あるポジションを任されることも少なくありません。収入面も他の建築士資格と比較して高水準で推移しやすく、将来の選択肢を広げる上でも重要な資産となる資格です。
一級建築士と二級建築士の違いは?
一級建築士は、扱える建物の構造や規模に制限がない点が最大の特徴です。二級建築士は木造住宅や比較的規模の小さい建物を中心に担当しますが、一級では公共施設や高層ビルまで設計・工事監理が可能となります。
こうした制限の有無は、担当できる業務の幅やキャリアの広がりに直結します。より高度な建築プロジェクトに携わることで、専門性だけでなくマネジメント能力も自然と磨かれます。
二級建築士も身近な住宅設計や小規模プロジェクトで活躍しますが、一級建築士を取得すれば、より大きな責任ある役割を担うことができるようになります。
将来的な成長機会や収入面で考えても、一級建築士資格の取得には大きな価値があるといえるでしょう。
一級建築士の平均年収は?
2019年に厚生労働省が発表した賃金構造基本統計調査で確認すると、一級建築士の平均年収は約700万円です※厚生労働省「賃金構造基本統計調査(2019年)」より抜粋
ただこの年収はあくまで平均値であり、実際の年収は「勤務先の企業規模」「担当するプロジェクトの規模」「役職」「経験年数」などによって大きく異なります。
たとえば、大手ゼネコンや設計事務所で管理職として勤務している場合は年収800万円〜1,000万円を超えることも珍しくありません。一方で、地域密着型の中小企業に勤務する場合は500万円〜600万円台にとどまるケースもあります。
つまり、一級建築士は「資格を活かす働き方」や「選ぶ職場」によって収入の幅が大きく広がる職種です。
資格の特徴と業務範囲
一級建築士は構造計算や建築計画、空調や照明など建築物に関する幅広い知識を習得しています。法規への適合性や工事監理のポイントを総合的に判断できるため、プロジェクト全体を見渡すアドバイザー的な役割を担うことも多いです。
また建築主との打ち合わせから竣工に至るまでのあらゆる工程に関わることができる利点があり、プロジェクトの中心として調整力を発揮できます。人命や財産を預かる建物ですから、その責任は非常に重いものの、やりがいも大きい仕事です。
こうした業務範囲の広さと責任の重さが、一級建築士の社会的ステータスを押し上げている要因ともいえます。建築文化の向上と安全を支える重要な資格として、常に高い需要が見込まれています。
年収アップ・キャリアパスへの影響
一級建築士は企業内での昇進スピードやキャリアパスの幅を広げる大きな要素になります。特に総合建設会社や大手設計事務所では、一級建築士を持つことがマネジメント層や専門職リーダーへの昇進条件になるケースもあります。
キャリアの選択肢が豊富という点は大きな魅力であり、住宅系、公共施設、医療福祉施設などの専門領域を深めながら専門家としての道を進むことも可能です。フリーランスとして自分の事務所を立ち上げる際にも、一級建築士の資格は信用を得る上で非常に有利に働きます。
結果として資格取得が年収アップにつながりやすいだけでなく、自己実現ややりたい建築の実現にも寄与してくれます。将来にわたって安定的に活躍できる専門家として、長期的に見ても資格取得の価値は高いといえるでしょう。
一級建築士試験の受験資格について
一級建築士試験を受験するには、学歴要件や実務経験の年数など複数の条件をクリアする必要があります。
受験資格を確認せずに勉強を始めてしまうと、いざ試験申込をしようとしたときに要件を満たしていないという事態になりかねません。大学や専門学校における専攻科目と実務経験の関係はとても重要で、学歴に応じて必要となる実務年数が変化します。
近年は法改正により、実務経験が受験要件ではなく登録要件として扱われるようになりました。この点は受験資格を得る上で大きな変更点となり、試験合格後も一定期間の実務を積まなければ正式な登録ができない仕組みです。
正確な要件は毎年更新される可能性があるため、建築技術教育普及センターの公式情報をこまめに確認することが大切です。事前に必要書類を揃え、受験資格を漏れなくクリアしたうえで試験準備に集中しましょう。
学歴要件と指定科目
大学や専門学校で建築系の指定科目を修了した方は、受験資格を得るうえで有利になります。例えば建築設計や構造力学など、カリキュラムの内容が一級建築士試験の出題領域と重なるため、知識ベースが作りやすいというまとめもあります。
一方で、文系出身や建築と直接関連しない学位を持つ方の場合、該当する指定科目を履修していないと受験資格を得られない場合があります。学歴による細かな要件が存在するため、事前にどの指定科目が求められるかをしっかりチェックすることが重要です。
もし不足している科目がある場合でも、通信制の講義や別の学習機関で単位を取得することで要件を満たす道もあります。早めに自分の学歴と科目履修状況を確認し、必要な手続きを進めることがスムーズな受験への近道です。
実務経験の要件と年数
一級建築士の登録には実務経験が欠かせませんが、試験を受けるタイミングで必ずしも全ての年数を満たす必要がないという点は重要です。令和2年の法改正により、試験合格後に必要な期間の実務経験を積むことでも最終登録の要件を満たせるようになりました。
ただし、実務の内容が建築設計や工事監理など適切な分野であることが求められます。単なる事務作業や全く異なる職種での経験は実務として認められない場合があるため、職場選びや業務内容に注意が必要です。
法改正以前とは要件が変わっているため、最新の情報を公式サイトや関連機関で確認し、実務経験の証明に必要となる書類をしっかりと準備しましょう。特に証明書類の不備や不正確な記載は登録手続きで大きなトラブルにつながりかねません。
試験スケジュールと合格率の実情
一級建築士試験は学科と設計製図の二段階で行われ、それぞれの直近の試験日程や合格率を把握することが学習計画を立てる第一歩です。
学科試験は例年7月頃に行われ、合格発表後には設計製図試験が秋から冬にかけて実施されるのが通例です。受験申込期間や試験日、合格発表日の情報は年度によって微妙に変わるため、建築技術教育普及センターなどの公式サイトを定期的にチェックすることが欠かせません。
合格率は年によって変動はありますが、難関資格としておおむね低めの水準で推移しています。例えば学科試験を突破しても、設計製図試験での合格が思うように得られず、複数年かけて挑戦する方も少なくありません。
過去の統計を見ても、一度で両方に合格するのは決して簡単ではありません。とはいえ合格率の推移を把握しておくことで、自分がどの程度の勉強時間を確保すべきか、どのレベルまで仕上げる必要があるかを実感しやすくなります。
受験申込期間・試験日・合格発表日
一級建築士の受験申込期間や試験日程は、毎年建築技術教育普及センターのウェブサイトで公開されます。インターネット受付と郵送受付の時期が設定されており、期限を過ぎると一切受け付けてもらえないため注意が必要です。
受験票が届いたら試験会場や持ち物を再確認し、余裕を持って当日に備えましょう。特に大都市では試験会場までのアクセスに時間がかかることもあるため、事前に所要時間を把握しておくと安心です。
合格発表は学科試験、設計製図試験ともに専用サイトや郵送で行われます。学科試験合格者のみが設計製図試験を受験できるという流れになっており、スケジュール管理が資格取得の鍵となります。
過去の合格率と難易度
一級建築士試験の合格率は年度によって変動するものの、総合的には難関資格として知られています。特に設計製図試験は学科試験とは異なる実務的なスキルを問われるため、独学では対策が難しいと感じる方も多いです。
学科試験で合格ラインをクリアしても、設計製図で不合格となり、次年度に再挑戦するケースも珍しくありません。ただし、一度学科試験に合格すると一定期間は学科免除の制度があるため、その間に設計製図対策を集中して行うことが可能です。
このように複雑な合格システムがあるからこそ、試験全体の難易度が高く感じられます。しかし対策講座や過去問演習を計画的に行うことで合格率を上げることは十分可能で、継続的な学習と適切な情報収集が合格への近道となります。
令和6年(2024年)の試験結果
| 試験区分 | 合格率 |
|---|---|
| 学科試験 | 23.3% |
| 設計製図試験 | 26.6% |
| 学科+製図(総合) | 8.8% |
※ 出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター(令和6年試験結果より)
一級建築士学科試験の重要ポイント
学科試験は出題範囲が幅広く、建築計画や構造、法規、環境・設備など多岐にわたる知識が要求されます。
学科試験では法令集を参照しながら問題を解く形式もあり、法規の正確な読み解きがポイントとなります。特に建築基準法や関連規則の改正情報は毎年アップデートされるため、常に最新の法令に触れておくことが重要です。
また、出題科目ごとに配点が異なるため、苦手分野を放置すると全体の合格点に達しにくくなる可能性があります。科目間のバランスを考慮しながら学習計画を組むことで、効率よく必要な得点を確保できます。
学科試験は時間配分との戦いでもあります。早めに過去問を解いて問題形式に慣れ、試験本番でスムーズに解答を進められるように対策することが不可欠です。
出題科目・配点と出題傾向
学科試験は建築計画や環境・設備、法規、構造、施工といった複数の分野からまんべんなく出題されます。配点の大きい法規や構造を中心に対策を進めるのが効率的ですが、他の科目も必ず一定数の問題が出るため総合力が求められます。
年度ごとの出題傾向をつかむためには、まず過去問を徹底的に分析することが基本です。法改正により内容が変わる場合もあるので、新旧の問題を比較しながら継続的にアップデートされた知識を身につけましょう。
また、試験では暗記だけでなく設計の実務感覚も問われる傾向があります。単純な知識に留まらず、実際の建築物のイメージをもって解ける問題が増えているため、普段から建築プロジェクトのケーススタディを行うと理解が深まります。
合格基準と学習対策
学科試験では、各科目ごとに一定の得点を確保しつつ、総合点でも基準点に達する必要があります。特定の科目だけ飛び抜けて点数が高くても、他の科目の合格基準を下回ると合格できないため、全体をバランスよく伸ばす戦略が重要です。
学習対策としては、独学か予備校に通うかの選択があり、それぞれにまとめがあります。独学は費用を抑えられますがモチベーション維持が難しく、予備校では最新の資料や講師の指導が得られる反面、コストがかかる傾向にあります。
いずれの方法を選ぶにしても、この段階で力を尽くして合格することで設計製図試験へ弾みをつけることができます。早期に合格点へ到達できるよう、学習計画をしっかり立て、過去問演習と理論知識のインプットを並行して進めましょう。
設計製図試験の概要と合格の鍵
設計製図試験は、一級建築士としての実務的なスキルを確認する重要なプロセスであり、図面の読みやすさや設計意図の明確さが合否を大きく左右します。
学科試験を合格した後に行われる二次試験の位置づけであり、実際の業務に近い形で建築計画能力を問われるのが特徴です。与えられた課題条件に沿って設計図書を作成し、高い完成度を求められます。
思考過程を限られた時間内で形に落とし込む必要があるため、素早く要点を把握し、ミスなく製図できる実践力が重要です。独学では合格を勝ち取りにくいと言われることも多く、予備校や講座に通って図面の添削を受ける方が増えています。
試験対策では過去問の課題に取り組み、傾向を分析することが重要です。基本的な図面作成能力はもちろん、プランニングや法規への適正判断など複合的なスキルが求められるため、総合力が試される試験だといえます。
課題発表の時期と過去問の特徴
設計製図試験の課題は毎年公表されるため、いち早く情報を入手して対策を始めることが肝心です。課題のテーマには公共施設や集合住宅など多種多様な事例があり、年度ごとに求められるポイントが微妙に異なります。
過去問の特徴としては、都市計画の視点を取り入れたものや、建築基準法の特定条文に配慮が必要な設計などが例として挙げられます。複数年分を解く中で共通する問題意識や設計条件を掴むことで、本番に向けた判断力が磨かれます。
課題の傾向を把握したら、自分なりに図面を描き込み、添削を受けることが大切です。時間内に効率的に図面を仕上げる練習を積めば、試験当日の集中力アップにもつながります。
一級建築士が活躍する企業三選
一級建築士としてキャリアを築く上でとくに重要なのは、「どこで働くか」。資格を活かせる職場は幅広くありますが、自分の価値を最大限発揮できる環境を選ぶことで、年収アップ・働きやすさ・経験が大きく変わってきます。
目的別に「稼げる」・「働きやすい」・「経験が積める」の3つの観点から、一級建築士が活躍しやすい代表的な企業カテゴリをご紹介します。
【稼げる】:大手ゼネコン
大手ゼネコンは、年収水準が業界トップクラス。
一級建築士としての実務経験を積んでいけば、年収800万円〜1,000万円以上も狙える環境です。大規模プロジェクトの企画・設計・監理に携わるチャンスも豊富で、キャリアアップを目指すには最適なステージといえるでしょう。
| ポイント | |
|---|---|
| 収入面 | 管理職や設計責任者などで高年収が期待できる |
| スキル要件 | 高度な技術力とマネジメント力が求められる |
| 職場環境 | 福利厚生や教育制度も充実 |
【働きやすい】:ハウスメーカー・住宅系企業
ハウスメーカーは比較的ワークライフバランスが整っており、子育て中の方や女性建築士にも人気です。
設計業務だけでなく、お客様との打ち合わせやプランニングにも関われるため、「人と向き合う設計」を大切にしたい方に向いています。
| ポイント | |
|---|---|
| 制度の充実 | 土日休み・フレックス制度・育休復帰実績など制度が整っている |
| スキルの安定成長 | 住宅設計のスキルを安定して磨ける |
| 提案の自由度 | 顧客志向が強く、設計提案の自由度が高い企業も多い |
【経験が積める】設計事務所・ベンチャー建築会社
独立志向のある方や、自分の色を出した設計をしたい方に人気なのが設計事務所や建築系スタートアップ。
少数精鋭の組織が多いため、若手でも責任ある仕事を任せてもらいやすく、実力次第でスピード感のある成長が期待できます。
| ポイント | |
|---|---|
| 独立志向に強い | 独立・開業を視野に入れた経験が積める |
| 裁量の大きさ | 一人ひとりの裁量が大きく、設計の幅も広い |
| 評価のされやすさ | 年収は成果主義だが、評価されやすい |
まとめ・総括
一級建築士資格の取得は、建築業界での専門的な地位を確立する大きな一歩であり、長期的なキャリア形成においても非常に有益です。
本記事では、一級建築士の資格概要や試験の流れ、合格率の現状から学科・設計製図試験の重要ポイントなどを総合的に紹介しました。学歴要件や実務経験の確認、法改正への対応など、準備段階から慎重に取り組むことが合格・取得への近道となります。
また、資格取得の先に広がるキャリアは多種多様で、設計・監理を担う技術者やプロジェクトを統括するマネージャー、審査機関のスペシャリストなどさまざまです。いずれの道へ進むにせよ、学習と実務の両面で得た知識と経験が今後の仕事の土台となるでしょう。
難関資格ではありますが、対策講座や過去問研究を積み重ね、継続的に学習することで合格に近づけます。ぜひ早めに準備を始め、あなたの理想のキャリアを実現するために一級建築士資格取得への第一歩を踏み出してください。
また取得した際や資格保有者で転職を検討する場合は、いつでもご相談ください。