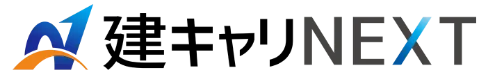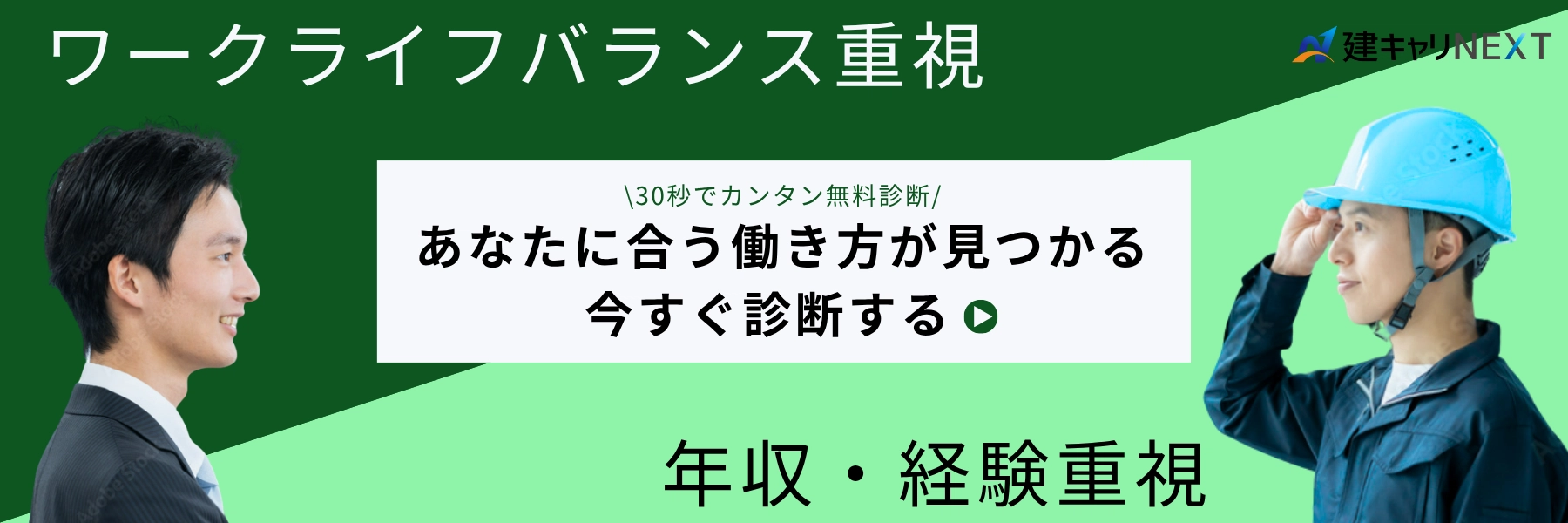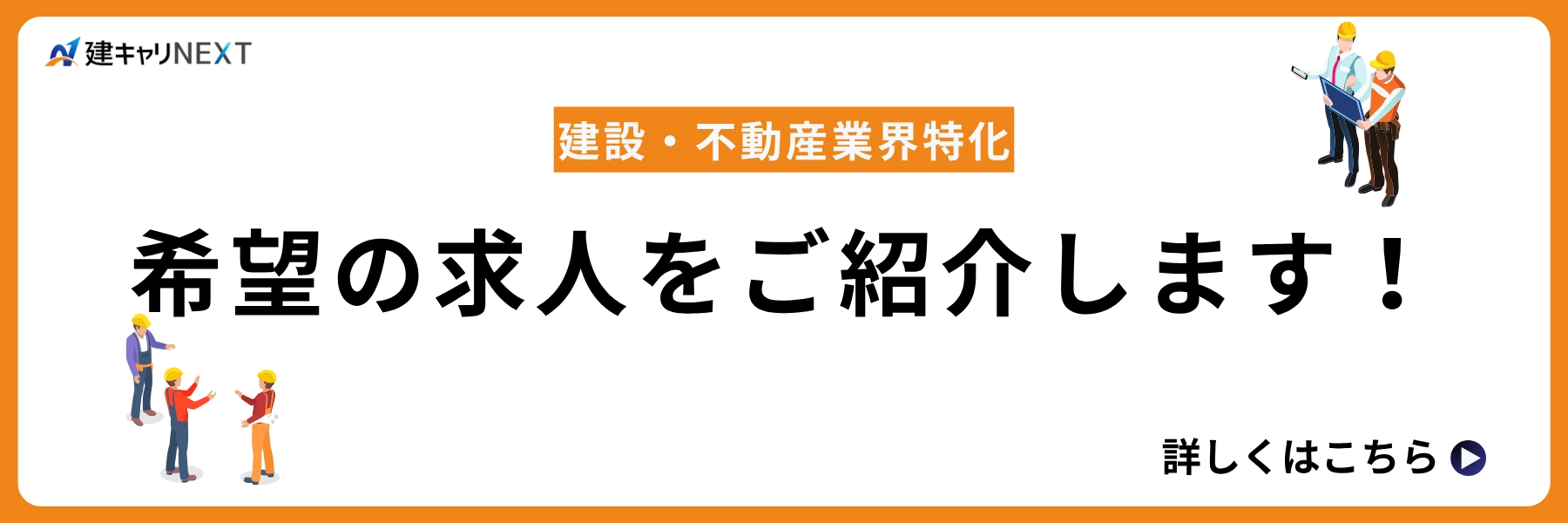【2025年最新】建設コンサルタント年収ランキング|働き方・業務内容・転職の方法を徹底解説
更新日:2025年12月20日

記事まとめ(要約)
- 建設コンサルタントは平均年収が高めで安定性が高い一方、施工管理は大手・残業手当で年収上振れも可能。
- 働き方は、コンサル=上流・デスクワーク中心/施工管理=現場常駐・手当厚め と明確に異なる。
- 転職する場合は技術士・RCCM等の資格取得と業界特化エージェントの活用。
「建設コンサルタントの年収はどれくらい?」「他の建設業界の職種と比べて高いの?」──建設業界でキャリア形成を考えている方なら、一度は気になる疑問ではないでしょうか。 本記事では2025年最新の建設コンサルタント年収ランキングを紹介するとともに、仕事内容や働き方、そして転職を成功させる方法まで徹底的に解説します。 これから建設コンサルタントを目指す方や、キャリアチェンジを検討している方はぜひ参考にしてください。

建キャリNEXT シニアコンサルタント
梶井 龍一郎
大学を卒業後、企画営業に従事
転職し20年以上人材業界に携わる。
現在は技術者をメインとしたキャリアサポートと人材教育を10年以上行っており、
累計6,000人以上の転職支援をサポートしている。
東京都出身、二児の父。
建設コンサルタントとは?
建設コンサルタントは、道路・橋梁・ダム・都市計画など 社会インフラの企画・調査・設計・維持管理を担う専門職です。 ゼネコンやサブコンが「施工」を担うのに対し、コンサルタントは上流工程から関わり、 発注者に近い立場でプロジェクト全体を支えます。
建設コンサルタントの定義
建設コンサルタントは、道路・橋梁・ダム・都市開発・上下水道といった社会インフラの企画・調査・設計・維持管理に携わる専門家です。 国土交通省に登録されている「建設コンサルタント登録部門」には21分野(鋼構造及びコンクリート、河川砂防、都市計画など)があり、それぞれの専門性に応じて活躍します。
建設コンサルタントの役割
ゼネコンやサブコンが「施工」を担うのに対し、建設コンサルタントは発注者(国・自治体・民間企業)の立場に近い上流工程を担当します。 具体的には、調査や計画立案、設計、施工監理、維持管理計画といった「ものづくりの前工程」を支える存在であり、社会インフラの安全性と品質を左右する重要な役割を担います。
他職種との違い
施工管理職や設計職と比較すると、建設コンサルタントはデスクワークの比率が高く、夜勤はほぼ無く、突発的な残業が少ないのが特徴です。 一方で、クライアント折衝や官公庁との調整業務が多く、論理的思考力・プレゼン力・調整力が求められる点に違いがあります。
【2025年最新】建設コンサルタント年収ランキング
建設コンサルタント業界の大手10社を平均年収ランキング形式でご紹介します。
企業ごとに年収水準や待遇に差があるため、転職を検討する際は事前にしっかりと確認しておくことが重要です。
| 順位 | 企業名 | 平均年収(万円) |
|---|---|---|
| 1 | 株式会社パシフィックコンサルタンツ | 960 |
| 2 | 株式会社日本工営 | 920 |
| 3 | 株式会社建設技術研究所(CTI) | 880 |
| 4 | 株式会社オリエンタルコンサルタンツ | 850 |
| 5 | 株式会社エイト日本技術開発 | 820 |
| 6 | 株式会社長大 | 800 |
| 7 | 株式会社復建調査設計 | 780 |
| 8 | 株式会社国際航業 | 760 |
| 9 | 中央復建コンサルタンツ株式会社 | 740 |
| 10 | 株式会社東京建設コンサルタント | 720 |
建設コンサルタントの働き方とキャリアパス
働き方の特徴
・デスクワーク中心:設計・解析・資料作成がメイン
・現場出張はあるが施工管理より頻度は少ない
・夜勤はほぼなく、ワークライフバランスを確保しやすい
このように、働き方は比較的安定している一方、繁忙期には納期対応で残業が増える傾向があります。
キャリアパス
若手時代は調査・設計補助からスタートし、経験を積むにつれてプロジェクトマネージャーや部門責任者へ昇進します。 また、公共工事を多く扱うため技術士資格の取得がキャリアアップの必須条件とされるケースが多いです。 さらに、海外インフラ案件に携わる機会もあり、グローバルに活躍できる可能性もあります。
建設コンサルタントへの転職方法は?
転職市場の動向
建設コンサルタント業界は、慢性的な人材不足が続いています。 そのため、20代後半〜30代の即戦力層はもちろん、40代以降のベテラン人材にも需要が高いのが特徴です。 特に一級建築士・技術士・RCCMなどの資格保持者は、複数企業から同時にオファーを受けるケースも少なくありません。
求められるスキル
・官公庁や自治体との調整経験 ・土木・建築分野の専門知識 ・技術士・RCCMなどの資格 ・プレゼン・報告書作成能力 これらを備えている人材は、転職市場で年収アップを実現しやすい傾向にあります。
転職を成功させる方法
建設コンサルタントは専門性が高いため、業界特化型の転職エージェントを活用するのが近道です。 企業ごとの案件規模や働き方の違い、年収テーブルなど、一般公開されていない情報を得ることで、自分に合った転職先を選びやすくなります。
建設コンサルタントと施工管理の比較
「建設コンサルタントと施工管理、結局どちらを選ぶべきなのか?」──転職やキャリア形成を考える方にとって、この問いは避けて通れません。 私が行っているキャリア面談の中でも、「安定した働き方を重視すべきか、それとも高収入を狙うべきか」という相談は非常に多く寄せられています。 平均年収の水準、働き方のスタイル、キャリアの安定性などを以下の表にまとめました。あなたのキャリア選択の参考にしてください。
| 建設コンサルタント | 施工管理 |
|---|---|
| 平均年収の目安 | |
|
700万〜900万円 大手では900万円前後。公共案件が中心で安定性が高い。 |
500万〜750万円 大手ゼネコン勤務なら30代でも800万〜1,000万円超えも可能。残業代・夜勤手当が収入を押し上げる。 |
| 働き方の特徴 | |
|
デスクワーク中心 夜勤が少なくワークライフバランスを保ちやすい。官公庁との調整業務や資料作成が多い。 |
現場常駐型 工程・安全・品質管理を現場で担う。残業や休日出勤もあり、体力的負担は大きい。 |
| 収入の伸び方 | |
|
資格・年次に応じて上昇 技術士・RCCM資格で年収アップ。成果より資格評価が重視されやすい。 |
残業代と案件規模で変動 1級施工管理技士資格で昇給。大規模案件や夜勤が多いほど収入が増える傾向。 |
| キャリアの安定性 | |
|
安定性が高い 公共インフラ案件が中心で、景気変動に左右されにくい。 |
プロジェクト依存 案件の受注状況に収入が左右される。ゼネコン勤務は安定性が高いが、中小では波がある。 |
| 結論 | |
|
平均年収では建設コンサルタントがやや優位だが、 |
|
まとめ|建設コンサルタントと施工管理、キャリア選択のポイント
建設コンサルタントは、社会インフラを支える専門職として 高水準の年収と安定性を兼ね備えた魅力ある職種です。 一方で施工管理も、大手ゼネコン勤務であれば年収1,000万円超を狙える可能性があり、 「安定志向ならコンサルタント」「高収入志向なら施工管理」という選択肢が見えてきます。
重要なのは、自分がどのような働き方・収入を優先するのかを明確にすることです。 建設コンサルタントは資格取得(技術士・RCCM)によって年収が上がりやすく、施工管理は経験年数や現場規模で収入が大きく変動します。 いずれの道を選ぶにしても、転職市場の情報を押さえ、専門エージェントを活用することが、キャリアを成功させる最大のポイントです。
今後ますます需要が高まる建設業界において、自分に合ったキャリアパスを選び、 「安定」か「高収入」かを意識した戦略的な転職活動を行うことで、将来の可能性は大きく広がります。 次の一歩を踏み出すために、まずは情報収集から始めてみましょう。